株式会社一番大切なこと
私のコーチとして使命は、『苦悩に値する働く意味』の創出です。
地球は平らだと信じていたがために出帆しなかった船は、どれくらいあるだろう?
信じているものが見えるものを限定し、見えるものは打ち手を限定し、打ち手は当然のことながら、望でいる結果が手に入るかどうかを決定付けます。あなたは何を信じてビジネスしてる?

社員の成長と組織力強化を目指し、2024年10月より経営層がICTC(Internal Coach Training Center)プログラムを導入。本記事では、同社の武田常務取締役と関根取締役に、プログラムを通じて得られた具体的な成果や組織の変化について詳しく伺った。
【インタビュアー】
本日はよろしくお願いいたします。早速ですが、貴社では2024年10月からICTCプログラムを導入されたと伺いました。
まずはプログラムを通じて、社内にどのような良い変化があったか、うまくいったことからお聞かせいただけますでしょうか。
【武田常務取締役】
はい。まず、ICTCで学んだことを活かし、社内で「すごい会議」を正式に実施できるようになったことが大きいですね。
これにより、社内に新しいコーチング文化を広める土台ができました。
また、私自身がコーチング技術を日常業務で積極的に使うことで、チームメンバーの成長を主体的に支援できるようになったと感じています。
結果として、メンバーが自ら課題を見つけ、解決していくという好循環が生まれています。

【インタビュアー】
素晴らしいですね。特に、武田常務がコーチングを実践されたことで、チームメンバーの方に目に見える変化はありましたか?
例えば、具体的な実績や数字面での向上などがあれば、ぜひお伺いしたいです。
【武田常務取締役】
ええ、顕著な例が2名います。一人は和嶋という社員で、コーチングを通じて自信と能力が大きく向上し、今では自分の意見を堂々と発言できるようになりました。
問題解決能力も格段に上がり、それに伴って数字も劇的に変化しています。対前年粗利益が、2,320万円から2,980万円まで増加しています。
もう一人の国又という社員も、自ら意思決定する力が飛躍的に向上し、彼の対前年粗利益は2,590万円から5,190万円にまで大きく伸長しました。
【インタビュアー】
お二人とも素晴らしい成果ですね。驚くべきは、このお二人はICTCプログラムを直接受講されたわけではないのですよね?
【武田常務取締役】
はい、彼らは受講していません。私たちがICTCで学んだコーチングを彼らに実践した結果、これだけの成長が見られたということです。
彼らは「すごい会議」にオブザーバーとして参加することはありますが 、主体はあくまで私のコーチングによるアプローチです。部下たちが生き生きと仕事に取り組む姿を見られるのは、私にとっても大きな喜びですね。

【インタビュアー】
武田常務のコーチングが具体的な数字としてチームに反映されているのですね。関根取締役はいかがでしょうか。ICTCの学びを活かして、特に大きな成果が出た事例はありますか。
【関根取締役】
はい。私が担当するリフォーム部門では、2025年3月には単月の売上・粗利益ともに過去最高を記録することができました。 これは非常に大きな成果だと捉えています。
また、ICTCを導入したことで、会議の進め方にも変化がありました。週次や月次の「すごい会議」で、必ず「うまくいっていることの共有」から始めるようにしたのです。
これを徹底することで、チームに前進感が生まれ、意見が活発に出て場の雰囲気も明るくなるという効果を実感しています。 この手法は、今では他のミーティングでも必ず取り入れるようにしています。

【インタビュアー】
これだけの成果が出ている背景には、皆さん自身の内面的な変化も大きいのではないでしょうか。
特に、部下と日々接する上でのご自身のあり方や、コミュニケーションの本質的な部分で、ICTC導入前後で最も変わった点は何だと感じますか?
【関根取締役】
まさに「上司」というあり方そのものが変わりましたね。ICTCを受けてからは、常に「私はコーチである」ということを自分に言い聞かせています。
もちろん、人間ですから部下に対して「この野郎!」と感情的になりそうな瞬間もあります。ですが、そんな時こそ「私はコーチだ」と一呼吸置くことで、ブレずに関わることができていると感じます。

【インタビュアー】
「コーチである」と意識することで、部下へのアプローチは具体的にどのように変わったのでしょうか。
以前のように上から指示するのではなく、相手の中から答えを引き出すような関わり方に変わった、ということでしょうか。
【関根取締役】
おっしゃる通りです。一方的に押さえつけるのではなく、常に対話を通じて本人の考えや可能性を引き出す。そのアプローチを常に心がけています。
【インタビュアー】
とはいえ、湧き上がった感情はどこかで消化する必要があるかと思いますが、どのようにバランスを取られているのですか?
【関根取締役】
「この野郎!」と感情的になったときは、武田に愚痴を聞いてもらっています笑。
【インタビュアー】
ICTCの学びを実践していく中で、難しさや課題を感じる場面もあったのではないでしょうか。
業務において「うまくいかなかった」と感じた経験についてお聞かせください。
【武田常務取締役】
はい、ありました。相手が目指したいゴールへとうまく導けなかったり、本質を引き出すような問いかけが瞬時にできなかったり、といった場面です。
後から振り返って『あの質問は効果的ではなかったな』と気づくことも少なくありませんでした。

【インタビュアー】
そうした壁にぶつかった時、どのように対処されていたのですか?
【武田常務取締役】
たとえ内心で迷いがあったとしても、相手の前では自信を持って接し、対話の中で軌道修正していくことを心がけていました。
【インタビュアー】
関根さんはいかがですか? コーチングを実践する上での難しさはありましたか。
【関根取締役】
始めた当初は、部下が立てた計画が明らかに目標達成には不十分だと感じても、否定できずに「本人が言うなら、まあやってみよう」と、もやもやしながら承認してしまったことがありました。
しかし、それではやはりインパクトのある成果には繋がりません。その点を大野コーチに相談した際に『気にくわないなら変えてもいい』とアドバイスをいただき、そこからは遠慮せず、より深く介入するようになりましたね。

【インタビュアー】
実践面でのご苦労があった一方で、ICTCプログラムの研修自体で大変だったことはありましたか?
【武田常務取締役】
それはもう、暗記の量ですね。非常に多くて苦労しました。
普段はほぼ毎日お酒を飲むのですが、覚えることに集中するために2週間ほど断酒して、必死で頭に叩き込みました。それくらい真剣でしたね。
【インタビュアー】
関根さんもやはり暗記で苦労されましたか?
【関根取締役】
はい、私も同じく暗記の部分で苦労しました。元々得意ではないので。
私の場合は、移動時間などを利用して、覚えるべきフレーズを何度も声に出して体に馴染ませるという方法で乗り越えました。
ICTCで使う独特の言い回しに慣れるまでには、少し時間が必要でしたね。

【インタビュアー】
様々なご苦労を乗り越えられた上で、率直に、ICTCプログラムを受けてよかったと思われますか?
【武田常務取締役】
はい、純粋に受けてよかったと感じています。これまで私は、営業メンバーの能力を上げるために「ティーチング」、つまり一方的に教えることしかできませんでした。
この方法だと、教えている間は成績が上がるのですが、私が離れると元に戻ってしまうという限界を感じていたのです。
しかし、コーチングを学んで実践すると、メンバーが自ら問題解決できるようになるため、一過性で終わらずに成長し続けてくれる。この違いは非常に大きいですね。

【インタビュアー】
「ティーチング」と「コーチング」、その根本的な違いはどこにあると、武田さんはお考えですか?
【武田常務取締役】
どちらも「人の行動を変える」という目的は同じだと思います。
ただ、ティーチングが「正しい答えを教える」という側面が強いのに対し、コーチングは相手自身に「問題意識に気づかせる」、あるいは「引き出す」ことで、自発的な行動を促す。
私たちは、相手が進むべき道筋を示す「道標」のような存在なのだと理解しています。
【インタビュアー】
関根さんは、ICTCを受けてよかった点をどのようにお感じですか?
【関根取締役】
これまでの経験で、なんとなく「こうすればうまくいく」という暗黙知は自分の中にありました。
ICTCを受けたことで、それらが明確に言語化され、なぜそうすべきなのかを論理的に他者へ説明できるようになったことが、一番の収穫です。
例えば、「目標を立てるメリットは何か」「問題とは何か」といった本質的な問いに、自信を持って答えられるようになりました。
また、「承認」と単なる「褒める」ことの違いも明確になり、実践しやすくなりましたね。

【インタビュアー】
ICTCでコーチングを学んだことは、既存の取り組みである「すごい会議」に対する見方にも変化をもたらしたのではないでしょうか。
【武田常務取締役】
まさしくその通りです。ICTC受講後は、大野コーチが「すごい会議」で展開するコーチングの一つひとつを、以前より遥かに深く理解できるようになりました。
そして何より、これまで会議に参加していなかった社員たちにもコーチングの考え方を応用して内容を伝えたり、彼らからの「これはどういうことですか?」という質問に的確に答えられるようになったりしたことが、組織にとって大きな前進だと感じています。
【関根取締役】
私も視点が全く変わりましたね。ICTC後は「自分だったらどうするか」というコーチの視点で会議に参加するようになりました。
大野コーチや森コーチが「なぜ今この質問をしたのか」「どのような振る舞いをしているのか」といった挙動を観察し、良いと思ったものは盗んで自分のものにする、という意識で臨んでいます。

【インタビュアー】
ICTCでの学びが、すでに行動変容としてチームに広がり始めている実感はありますか。
【関根取締役】
はい、非常に感じています。現在、社員の約8割を対象に、ICTCで学んだ手法を用いた会議やセッションを実施しています。
その対話を通じて、社員一人ひとりが自分の頭で考え、自立して日々の業務にフォーカスするようになったと感じます。
例えば、以前ならお客様からキャンセルが出るとそこで思考が止まっていたのが、今では「どのようにすればこの穴を埋められるか」と自ら考え、行動してくれる。この変化は非常に大きいですね。

【インタビュアー】
素晴らしい変化ですね。では、もしその輪がさらに広がり、社員一人ひとりがこのコーチングスキルを身につけたとしたら、貴社はどのような組織になるとお考えですか?
【武田常務取締役】
これまで「無理だ」と諦めていたような高い目標も、達成できる組織になるでしょうね。
そして、仕事の進め方そのものが変わり「不動産会社らしくない」と評されるような、独自のスタイルを確立できる気がします。
これまでの業界の常識や、なんとなくの経験則で動くのではなく、一人ひとりが本質を考えて行動する集団に変わっていくはずです。
【関根取締役】
私も武田の意見に近いですが、私は特にお客様との「関係性の質感」が大きく変わると考えています。
単なるサービス提供者と顧客ではなく、お客様が抱える問題を一緒に解決していく「一つのチーム」のような関係性を築けるようになるのではないでしょうか。
デジタル化が進み、人間関係が希薄になりがちな現代だからこそ、こうした質の高いアナログなコミュニケーションが、他にはない価値を生むと確信しています。

【インタビュアー】
素晴らしい未来像ですね。そこまで組織を変える力を持つICTCプログラムですが、お二人にとって、その本質的な「価値」とは何だったのでしょうか。
【武田常務取締役】
「自分の在り方を設定し、それに基づいて行動できること」、これに尽きると思います。
これまでは、自分自身の「在り方」を深く意識することはありませんでした。ICTCを通じてそれを意識できるようになったこと、それ自体が計り知れない価値だと感じています。

【関根取締役】
私は「元々、人はNICEな存在である」という考え方が根底にあると思います。
誰かがNICEに見えない時があるとしたら、それはその人本来の良さにうまくアクセスできていないだけ。
その人が最高の状態にアクセスできるよう支援することこそがコーチングであり、ICTCの価値だと考えています。
【インタビュアー】
なるほど、非常に本質的な価値ですね。では、このICTCプログラムを特にどのような課題を持つ企業に推薦したいとお考えですか?
【武田常務取締役】
これは、全ての企業に当てはまると思います。なぜなら、何らかの問題や課題を一切抱えていない企業というものは存在しないからです。
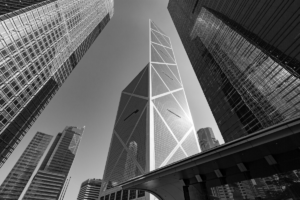
【関根取締役】
そうですね。これは業種や現場を問わず、知らないよりは知っていた方が間違いなくプラスになるスキルと考え方です。あらゆるビジネスパーソンにとって有益だと思います。
【インタビュアー】
それでは最後に、この記事を読んでICTCプログラムに関心を持った経営者やリーダーの方々へ、メッセージをお願いいたします。
【武田常務取締役】
もし、すでに「すごい会議」を導入されているのであれば、ぜひICTCもセットで受講されることを強くお勧めします。
プログラムへの理解度、ご自身の行動、そして得られる成果、そのすべてが劇的に変わるはずです。
【インタビュアー】
ありがとうございました。

【結論(まとめ)】
今回のインタビューで浮き彫りになったのは、「教える(ティーチング)」から「引き出す(コーチング)」への転換が、いかにして組織と個人のポテンシャルを解放するかという事実だった。
武田氏、関根氏の言葉から見えてくるのは、それが単なるコミュニケーションスキルの習得に留まらない、より根源的な変革であることだ。
「私はコーチである」という自己規定は、部下との関わり方を根底から変え、結果として目に見える数字の成果と、社員が自ら考えて動くという組織文化の醸成に繋がっている。
「2週間の断酒」というエピソードに象徴されるように、その変革は決して平坦な道ではなかった。しかし、その真摯な取り組みがあったからこそ、彼らの言葉には揺るぎない実感が宿る。
部下の成長に限界を感じている、あるいは組織の閉塞感を打破したいと願う全てのリーダーにとって、彼らの歩みは大きな示唆を与えてくれるだろう。
本当の組織変革は、手法やテクニックの前に、まずリーダー自身の「在り方」を問い直すことから始まるのかもしれない。

私のコーチとして使命は、『苦悩に値する働く意味』の創出です。
地球は平らだと信じていたがために出帆しなかった船は、どれくらいあるだろう?
信じているものが見えるものを限定し、見えるものは打ち手を限定し、打ち手は当然のことながら、望でいる結果が手に入るかどうかを決定付けます。あなたは何を信じてビジネスしてる?